こんにちは。
アスリート薬剤師のじんじんです。
今回は服薬指導風景シリーズです。
服薬指導風景シリーズも第13弾になりました。
いつものように、以下の点をご理解いただいた上でお読みください。
- プライバシーに配慮して、趣旨を逸脱しない範囲内で一部脚色等を施しています。
- あくまでもじんじんの個人的な経験であり、すべての方に一般化されるものではありません。
- 患者様お一人おひとりで状況は異なりますので、ご自身に置き換えて読まれる場合にはご注意ください。
- 本記事の内容を参考にして頂いたり、実際に真似て頂いたりした際に生じた結果について、当ブログおよびじんじんは一切の責任を負いません。
病気じゃないから薬はいらない〜30代の統合失調症患者さん〜

Aさん、こんにちは。

あ〜、じんじん先生。
なんで俺の名前呼んだの?

Aさんのお薬の準備ができたのでお呼びしたんですよ。

え?
この前も言ったと思うけど、俺は薬いらないよ。
病気じゃないって言ってるじゃん。

そうですか…。
でも今日は診察には来られたんですね。

だって予約入れられてたから。

やっぱりお薬は飲みたくないですかね?

別に飲みたくないわけじゃなくて、病気じゃないから要らないってこと。

そうですか…。
でも前回おいでになられた時にお渡しした夜の薬はどうされたんですか?

いや。
病気じゃないから薬は飲まなくていいんだけどね。
でもまぁ飲んだほうが熟睡できる感じがするから飲んだよ。

病気じゃないからお薬はいらないけど、この前の薬は飲んでみたらよく眠れたってことですね。

うん。
飲んだらあんまり色々考えないでスーッと眠れた感じかな。

そういう意味ではお薬にもメリットがあった?

まあね。
でも俺は病気じゃないんだよ。

なるほどですね。
今日はこの前と同じお薬を準備しています。
病気じゃないかもしれないけど、しっかり眠れるように今回もお薬飲んでくださいね。

寝るためだから飲んでもいいかな。
寝れないのはきついからね。
じんじんの服薬指導のポイント
- 患者さんの言う「病気じゃない」を頭ごなしに否定しない。
- 患者さんの言い分をしっかり聞く。
- 患者さんの困りごとに役に立てそうであれば、それをお伝えする。
精神科の病院では比較的よくある状況です。
もちろんすべての患者さんがそうだという訳ではありませんし、多くの患者さんがご自身の病気については理解しておられます。
でも、一部の患者さんにはご自身が病気であるという認識がありません。
それまでの経過やご家族など周囲の方からの情報、本人さんのおっしゃる症状(本人さんは症状とは思っていませんが)から、明らかに病的な状態であっても自覚されていないのです。
別にあえて否定しているわけでもないと思います。
実際に、病気であるという実感がないようです。
「病気じゃない」のだから、お薬だって飲みたくないわけです。
以前、じんじんの勤める病院に、総合病院の研修医の先生が研修に来られました。
その先生がおっしゃっていたことです。
我々の病院ではあり得ないことです。
だって、「病気じゃないから薬を飲みたくない」と言われたら「じゃあ、お引き取りください」ですもん。
でも、精神疾患のある患者さんだとそうじゃないんですね。
薬を飲んでもらうことから始めていかないといけないんですね。
病気じゃない、薬も飲みたくない。
でも病院には来る。
これって不思議なことに思いませんか?
でも、ここが鍵なんです。
患者さんは「病気ではない」と言う一方で、「何も困っていないわけではない」ということなのです。
「病気ではないんだけど、なんか上手くいかないんだよなぁ」という”困り感”は自覚されているケースが少なくありません。
じんじんはこの患者さんの”困り感”にフォーカスしてお話しさせていただくことが多いです。
結果として、お薬を飲むことに納得していただき、少しずつ信頼関係を築くことにつながっていきます。
”困り感” 意識しみてはいかがでしょうか?
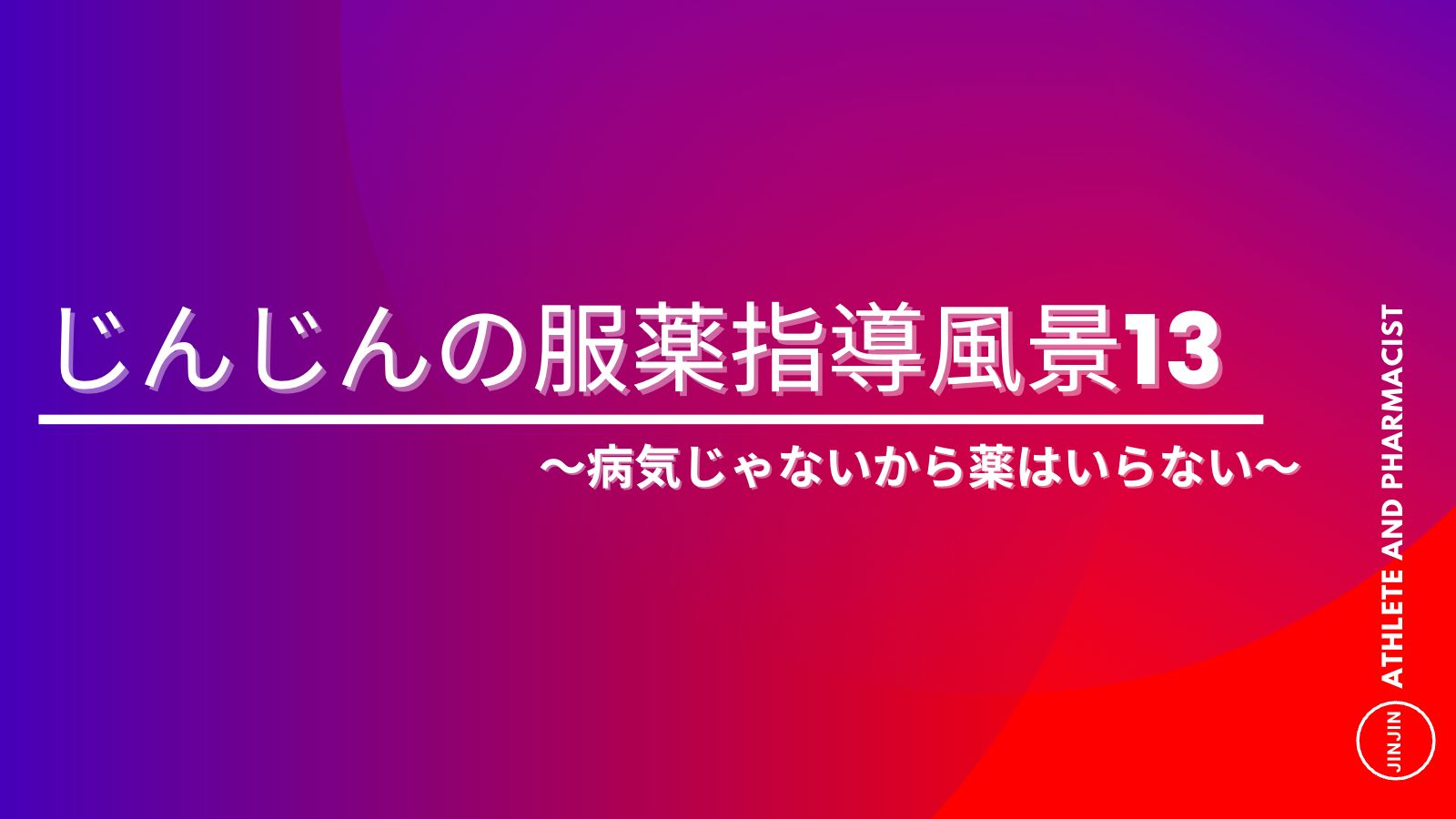
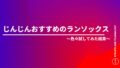

コメント