アスリート薬剤師のじんじんです。
じんじんは病院で薬剤師として働いていますが、繊細な方々と接する機会が増えてきています。
「繊細」と聞くと最近話題の「HSP」を思い浮かべる方も多いと思います。
HSPって?
HSPというのは簡単に説明しますとHighly Sensitive Personの略で、生まれつき非常に感受性が強く敏感な気質を持った人のことを指します。
アメリカの調査では5人に1人くらいはHSPにあてはまる可能性があるとされており、稀ではないものの、誰もが当てはまるというわけではなさそうです。
一般的に言われているHSPの特徴は次のようなものです。
- 深く情報処理を行う(場や空気を過剰に読む、文字列に意味を見出そうとするなどの特徴があります)
- 外部からの刺激に敏感(音やにおいなど、HSPではない人にとってはなんでもない刺激が非常に強く感じられてしまいます)
- 共感しやすい(周囲の人の感情を読み取り、自分を合わせる傾向があるとともに、感情移入もしやすいとされています)
- 影響されやすい(相手の感情に共感しやすかったり、感情移入しやすかったりすることから、相手に過剰に同調してしまいやすい)
- 疲れやすい(刺激に敏感であるため、HSPでない人の何倍もの刺激にさらされることになり、疲れやすくなります)
HSPの人はこういった特徴があるものの、目に見えるものではないため周囲の人に理解されにくいといえます。
また、本人の内面の感じ方の違いでもあることから他者にはわかりにくく、さらにはその程度や表れ方も個人差が大きいため、本人でさえも認識するのが難しいことがあります。
一方でHSPの特徴は長所でもあります。
- いろいろな事柄や情報を深く探究し、様々な視点から見ることができる
- 周囲の人の気持ちの変化に気づくことができるため、相手の立場で考えたり行動したりできる
- 映画やドラマ、音楽などに対してより大きな感動が得られたり、没頭できる
- まわりの変化に気づきやすく、速やかに対処行動が可能
繊細さは結構いいところ(長所)だと捉えられると良いですよね。もちろん苦手な部分が生活に影響を及ぼすこともあるかもしれませんが、今は多様性の時代です。
誰でも苦手な部分があって良いと思いますし、その苦手な部分がひとによって違って良いと思います。その誰かの苦手な部分を他の誰かが補いながら回っていく社会だといいですね。
 | 「繊細さん」の本 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる [ 武田友紀 ] 価格:1,324円 |
じんじんが出会った敏感な患者さん
そんな中、薬剤師として敏感な患者さんと接する機会があります。
必ずしもHSPのひとというわけではありません。
ここで話題にする敏感な方というのは口の中や喉の感覚が敏感な方です。
大人でも子供でもおられます。
「どういうこと?」と思われるかもしれませんが、お薬が飲めるかどうかに大きな影響があります。
30代の男性患者さんで、IT系の会社にお勤めで、とてもスマートな方です。
言葉も丁寧ですし、ご自身の気持ちをきちんと言葉で伝えてくださる患者さんです。
ある日その患者さんがじんじんにこう仰いました。
「今まで恥ずかしくて言えなかったんですけど、実は錠剤が飲めないんです。本当は良くないのかもしれないと思いながら、自分で砕いて飲んでいました。大の大人が錠剤が飲めないなんてみっともなくて言えませんでした。」
じんじんは全く予想外の告白に正直驚きました。
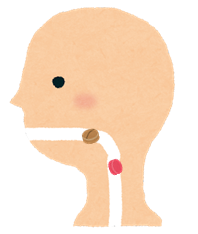
とりあえず錠剤が飲めない理由を尋ねたところ、
「口の中から喉を通って、食道を通り抜ける感覚がわかるんです。それがとても気持ち悪くて」
想像すると確かに気持ち悪い気がします。
自分の身体の中を固形物が移動していく感覚がリアルに感じられるというのは不快かもしれません。
そこでじんじんはその患者さんが飲んでおられるお薬について確認をしたところ、錠剤をつぶして粉にして飲んでも大丈夫であることがわかりました。
早速主治医に報告し「粉砕指示」を出してもらいました。
その日から、その患者さんには錠剤を粉砕して粉薬にしてお渡しできるようになり、大変喜んでいただけました。
薬剤師として
もちろん患者さんが自己判断で錠剤を砕いて服用していたというのは薬剤師としては心配なことです。
すべての錠剤のお薬がつぶしてよいものではなく、場合によっては効果がなくなったり、重大な副作用につながったりすることもあります。
でも、ここで患者さんを責めてしまっては薬剤師としていかがなものでしょう?
薬剤師がお薬そのものの知識があるだけの存在だとすると患者さんにとってはあまり必要性を感じられないのではないでしょうか?
Googleで調べたらお薬の情報なんていくらでも見つかります。
「お薬の情報をもとに、その患者さんの治療がうまく進むようにサポートすること」
これが薬剤師に必須のスキルだと思います。
今回の患者さんは錠剤が飲めない患者さんでした。
ほかにもカプセルが飲めない患者さん、粉薬が飲めない患者さんなど様々おられます。
1人ひとりに合わせてしっかりかりサポートしていくことが求められます。
今回のように錠剤をつぶして粉にするといった対応だけでなく、おすすめのオブラートをお伝えしたり、ゼリータイプの服薬補助食品をおすすめしたり、薬剤師さんならではのサポートはたくさんあります。
オブラートひとつとってもAmazonで「オブラート」と検索すると192件、服薬補助用のゼリーも「おくすり飲めたね」や「らくらく服薬ゼリー」など複数の商品がヒットします。
目の前の患者さんにはどの商品がおすすめなのか、ここは薬剤師の腕の見せ所です。
一方で患者さんの立場からは目の前の薬剤師さんがどれくらい頼りになるか見定める一つの物差しにもなるかもしれません。
まとめ
「治療なんだから無理にでも頑張って飲まなきゃいけない」

「飲めないなんて言っちゃだめ」
なんて考えとはこの際お別れしましょう。
繊細であること、敏感であることは誰が悪いわけでもないのです。
その結果としてできないこと、苦手なことがあるのなら、誰かにサポートしてもらって良いではないですか!
お薬を飲むのに苦労しておられる皆さん、ぜひ薬剤師さんに相談してみてください!
相談された薬剤師さんはぜひ患者さんの立場でサポートしていきましょう!
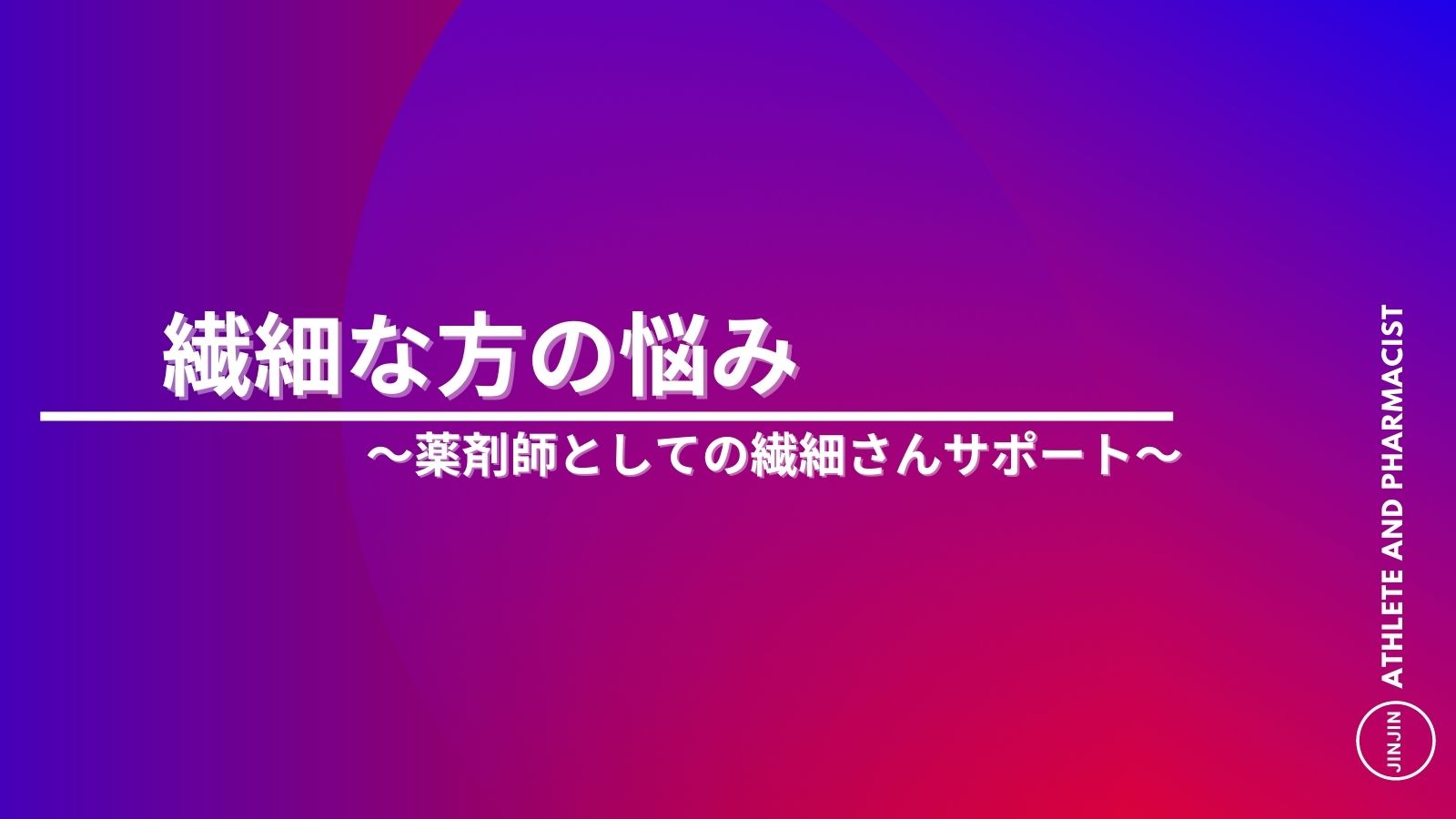


コメント